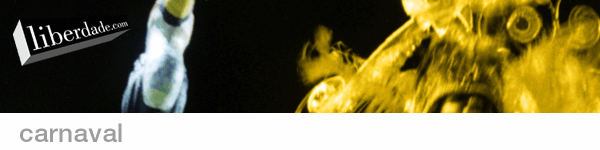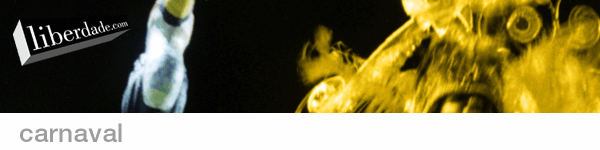|
ポルトガル語でCARNAVAL(カルナバル)、日本語でカーニバル。この単語は人を惹きつける何かがある。三十年前の映画「黒いオルフェ」は辺境の地ブラジルのカーニバルの異常な熱気を世界に伝えた。最近リメイクされた「オルフェウ」でもカーニバルが、ラテンアメリカの魔術的リアリズム、日本にはあり得ない空気が描かれていた。
カーニバルに関する話はまるでお伽噺のように聞こえる。
曰く、カリオカ(リオっ子)にとって一年はカーニバルの四日間のためにある。カリオカは一年間カーニバルに参加するのにかかるお金を貯めるために働く。あるいは、ブラジルではカーニバルから数えて十月十日後に生まれる子供が多い−−。
カーニバルは街の中心地に近い、サンボドロモと呼ばれる会場で行われる。会場の周りには、鉄の門が幾重にも設置されていた。空にはカクテル光線が交差し、大音響が聞こえる。
「どっから来たの? 美味しいよ」
会場の外では年端のいかない子供が屋台を出してソーセージを焼いている。古い落書きだらけの家の入り口には、痩せた老女が会場のほうを向いて足踏みをするように踊っているのが見えた。ブラジルでのいつものように、軽く会釈をしたが、反応はなかった。
「その婆さんは目が見えないよ」
道端にいた太った女性の売り子が言った。老女の足下では、犬が彼女を気遣うように首を振っていた。
会場の中では、十五万人の観客が立ち上がり、大声で歌を歌い、踊っていた。
腰を細かく振り目の前で踊る人々。全裸に近い褐色の若い女性、牛乳瓶の底のような分厚い眼鏡を掛けた黒人の老女、大声を張り上げて歌いながら歩く白人、東洋人の顔つきをした人も目につく。
意外だったのは、行進が整っていないことだったことだ。踊りはばらばら、自分の集団から迷って注意される人もいる。遠くから見ると壮麗だが、この国の多くの生産物と同じように近くで見るとほころびが目立つ。
カーニバルは、エスコーラ・ジ・サンバと呼ばれるサンバチームが行進の出来を競う。一つのサンバチームで二千人から三千人以上の人間が練り歩く。行進にはテーマがあり、それにあわせた仮装をしているのだ。
夜の九時から始まったカーニバル。一つのエスコーラ・ジ・サンバの持ち時間は1時間強。行進の間にはオレンジ色の制服を着た清掃員が踊りながら掃除をする。この日は七つのサンバチームが現れ、夜が明け空が白み太陽が昇るまで太鼓と踊りの大騒ぎが続いた。
−−確かに壮大な行列だった。
しかし、正直なところ拍子抜けした。派手、大人数、しかし、それだけだった。テレビや雑誌で見たカーニバルを確かめただけ、だった。
カーニバルが終わりに近づいた朝方、一人の警備員が声を掛けてきた。
「この時期になると、リオの街は日本人が沢山いるよな。どうしてこんなにカーニバルが好きなんだ。取材陣、観客席、そして行進の中にも。みんなわざわざ地球の裏側からやってくるんだろう」
男は本当に不思議なようだった。
「まあ日本人だけじゃないな。最近のカーニバルは観光化してしまって外国人がツアーを組んで金を払って参加する。金を持っているカリオカは街から逃げ出す。街に残っているのは俺たちみたいな貧乏なカリオカか、外国人観光客、それを目当てにブラジル国内から集まってきた売春婦さ」
僕たちは不幸な時代にいる。
多くの場所が想像の範囲内で収まってしまう。もはや辺境の地を舞台にした荒唐無稽な冒険映画や小説は存在しえない。リアリティがないからだ。世界中の商品になりえる場所はあっという間に消費されている。観光地になりえない辺境は辺境であり続けるが、それ以外はどんどん均質化している。
日本から見れは確かにリオは地球の裏側。しかし、リオのカーニバルは世界でも屈指の売れ筋商品だ。2002年、リオは辺境ではない。距離的には遠いが、世界の中では日本と同じ側にいるのだ。
リオのカーニバルは携帯電話片手の男が闊歩する巨大な見せ物に過ぎず、それ以上の何かは、なかった。
|