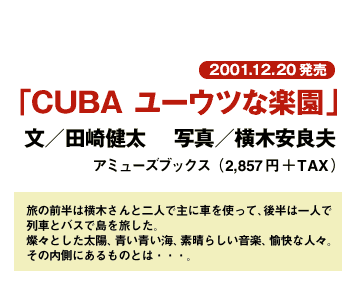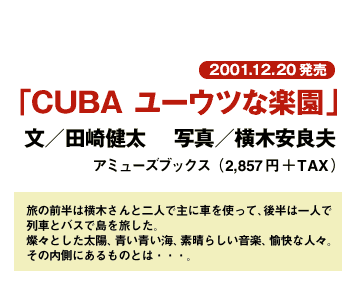|
初めてキューバの地を踏んだのは五年前のことだ。
キューバに初めて行きたいと思ったのはその随分前、僕が小学生の時。当時僕は、日本海側の港街に住んでいた。あの街の空は曇っていたという記憶しかない。もちろん、そんな訳はない。海辺を自転車で走った時も、小学校のグラウンドを駆け回って水道の蛇口から迸る水をむさぼり飲んだ時も、太陽がかんかんと照りつけていたはずだ。しかし、今思い出すのは曇り空。
日本海側の港街と太平洋側の港街はずいぶん違う。富める国アメリカ合衆国に向いた太平洋側、とすでに斜陽だったソビエト連邦に向いた日本海側。街を歩く外国人はロシア人船員でくすんでいた。街には、大きな造船所があった。ソビエトの力も衰えていたが、日本の造船も負けていなかった。造船所で働く父を持つ同級生が、父の仕事の都合で転校して行った。四月が来るたびにクラスから同級生が減った。街全体に灰色の空気が充満していたから、いつも曇っていたという印象しか残っていないのかもしれない。
ある日のことだ。友達の家に行った。彼の父は開業医で裕福だった。長い休みごとに僕たちの行ったことのない場所に連れて行ってもらっていた。彼の一家が北陸から帰ってきた後のことだったと思う。彼は雷鳥を見てきたと言った。図鑑の中でしか見たことのない珍しい鳥の様子を、彼は説明した。
雷鳥の話が一段落して、僕の目に部屋に飾られていた一枚の写真が目に入った。写真には、青い空の下の元で笑みをたたえた老夫婦が写っていた。その空の青さはこの街に似つかわしくなかった。
「これは誰? どこ?」
僕が尋ねると、友達は誇らしげな顔をした。
「キューバという国なんだ。おじいちゃんとおばあちゃんが住んでいる。大きくなったら会いに行くつもりでいるんだ」
僕は、港に出入りする船を見るのが好きだった。海の向こうに行ってみたいと思っていたが、あくまで遠い世界だった。
この街とは違って青い空を持つキューバという国に親戚を持つ彼がとても羨ましかった。雷鳥を見たこととは比べ物にならない程、羨ましかった。
それから二十年近くたった96年秋、出版社に務めていた僕は休暇を使って、キューバを訪れた。
ハバナの街には古く崩れかけた建物が建ち並んでいた。店には物はなく、道を歩く人はみんな色あせた服を着ていた。何より残念だったのは、空が青くなかったことだ。秋だったせいもあったが、灰色の空をしていた。アキ・カウリスマキ監督の映画「マッチ工場の少女」を連想するような、どんよりとした街という印象を持った。
その後僕は、出版社を一年間休職して南米の他の国を回った。出会った多くの人がキューバに行ってみたいと言った。行ったことがあると言うと、羨ましがられた。
キューバの様々なことを見逃していたのかもしれない、僕は思った。当時はスペイン語もあまり上手くなかった。また、一週間に満たない時間しかあの国で過ごしていない。僕は表面をなでただけで、どんよりとした街だと思いこんでいたのかもしれない。
それを確かめるために、2001年8月末、二十一世紀最初の夏の終わり、写真家の横木安良夫氏とともに再びキューバに降り立った。今度の滞在は三週間、たっぷりとこのカリブの島に浸かろうと考えていたのだ。
|