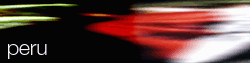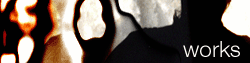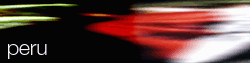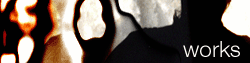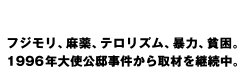|
一ヶ月遅れに現地に入るなんていうのは、転校生の気分だった。クラスの他の連中は、互いの存在を認め合い連帯感ができている。転校生ならば先生がみんなに紹介してくれるが、元来記者クラブに入っていないアウトサイダーである、週刊誌の記者に親切で思いやりのある先生などいるはずもない。
リマの日本大使公邸の周りには、テレビカメラや三脚が幾重にも置かれていた。もう場所は全て決められているようで、入り込む隙間はなかった。見張りと思しき混血の男が昼寝をしているのを横目に、黄色いテープが張られて立入禁止となっている周りを所在なく歩き回るしかなかった。
* * *
タラポトを出てから一時間が経とうしていた。日本製の古い4WDは最初は細かく、そしてだんだん大きく横揺れするようになっていた。地平線から太陽が顔を覗かせ、空の光の部分が次第に大きくなっていった。
「今日の取材は何時ごろ終わる?」
突然、後部座席、僕の隣に座っていたディアナが尋ねた。
「恐らく昼過ぎに終わるんじゃないかな」
「夕方のリマ行きの飛行機まで少し時間はあるわね」
「そう思うけれど」
ディアナは少しためらった後、思い切っていった。
「折角だから、タラポトの外れの滝に行ってみたいんだけれど……」
ディアナはリマに住む大学生だ。日系人ではないが、日本語を勉強していた。僕は、ペルーの公用語であるスペイン語を多少理解することはできた。しかし、旅行者として笑って許される程度は、仕事では笑って済まされない程度だ。
事件のために、二百人以上と言われる報道陣が日本から海を渡った。通訳の需要は供給の数をはるかに越えていた。他より随分遅れてこの地を踏んだ僕のために、通
訳を生業としている人間を残してくれているはずはない。不完全にスペイン語を分かる僕と、不完全に日本語が出来るディアナ。二人を合わせて当座を凌ぐしかないのだ。
「時間があれば、滝に行ってもいいよ」
僕は答えた。
「嬉しいわ。ペルーでは有名なところなのよ。昔から一度行ってみたかったの。私は、リマと生まれ故郷のアレキパ以外のペルーは知らないから」
ディアナは顔をほころばせた。
助手席に乗っていたアドルフォが後ろを振り返った。
「ワジャーガ河に到着だ」
丘の下には大蛇のようにうねった茶色の河が見えた。
|