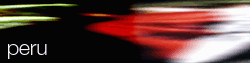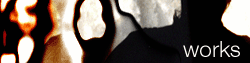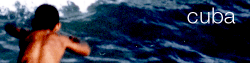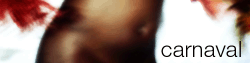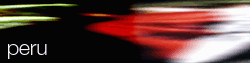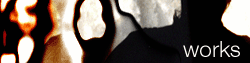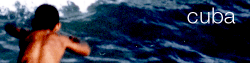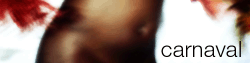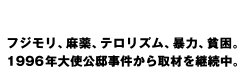|
頼りない街灯に照らされていた労働者の拳のように無骨なコンクリート造りの建物が周りから消えた。車が細かく揺れる。埃っぽいコンクリートの道が終わり、砂利道に変わったのだ。道の左右は深い闇に包まれている。しんしんと虫の鳴く声が聞こえる。
朝六時。まだ太陽は昇っていない。荷台に人を載せたピックアップトラックとすれ違った。細かな砂がぱっと巻き上がり、視界を遮った。ペルーの首都リマから北東に650キロ、空路1時間の距離にあるサンマルティン県のタラポトという村の外れを走っていた。
ペルー、コロンビア、ブラジル、南米大陸を緑で覆うアマゾン地帯。ブラジルのマナウス、ペルーのイキトスなど幾つか滲みのように都市がある以外、大部分では未だ人を寄せ付けない。緑の洪水の中で滲みにもならない小さな村、タラポトの街。
* * *
一ヶ月程、前に遡る。
1996年12月23日、リマの日本大使公邸。六百人を集めたパーティが開かれた。
AKMと爆薬で武装したMRTA(トゥパク・アマル革命運動)の兵士たちは、パーティを急襲し招待客を人質として立て籠もった。
週刊誌の特派員として、僕がリマに到着したのは、事件から丁度一ヶ月経った頃だった。この雑誌の最初の特派員だった。
12月から1月にかけて週刊誌は週刊でなくなる。週刊誌の購買層である会社員の休暇に合わせ、合併号と呼ぶ年末年始向けの変則的な発売になる。事件が起こった23日の時点では、年内最終号の締め切りは終わっていた。次号、新年明けの合併号の締め切りには二週間。それまでには、解決しているだろうと、編集部は予想していたのだ。
ところが、年が明けても、七十人強の人質を囲い込んだままだった。
事件は、完全に膠着状態に入っていた。週刊誌の企画というものは慢性的に不足している。いや、たとえ充足していても、不足しているのではないかという恐怖感を感じるといってもいい。体質的に欠乏症であるのだ。正月明け、他に取り立てて大事件もないからリマに人を送ったらどうか、そんな話になったのだろう。
選ばれたのが、六月から一年の休暇を申請していた僕だった。
一年の休暇は、出版社の制度としては認められていたが、編集部内の共通意識として認められるわけもない。休暇を申請してから、一ヶ月半ほど、仕事がなかった。なかったというのは正確な言い方ではない。出す企画、出す企画ことごとく通
らないのだ。週刊誌にうんざりとしていた僕の企画がつまらないこともあったろう。しかし、それ以上に故意的に僕に仕事をさせないという意志を感じた。
週刊誌の編集部員にとって仕事がないこと程辛いことはない。仕事がないから編集部に居なくてもいいというわけではないのだ。他が殺気立っているところで、僕は電話を取ったり事務処理をして、冷たい視線に耐えなければならない。
しかし、一人の編集部員をこれから六月まで半年のあいだ、仕事をさせないというのも無理がある。ペルー行きは懲罰の適当な落としどころだったのだ。
|