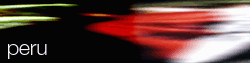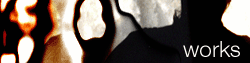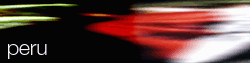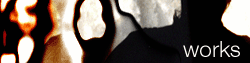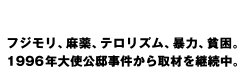|
リマに着いてから一週間ほどは物珍しさもあって、自分の感じた状況を東京の編集部に書き送った。しかし、それはすぐに行き詰まった。多少の動きはあれど、事件は膠着状態だ。それ程ニュースがあるわけもない。リマの日本大使公邸前では、各社とも数十人で取材体制を組んでいる。とてもじゃないが僕一人で大使公邸前で待っていても、太刀打ちできるはずもない。
一ヶ月遅れの転校生は周りに全く溶け込むことはできなかった。
そんな時、『エル・コメルシオ』紙の特捜班に所属するミゲルと知り合った。『エル・コメルシオ』紙は百年以上の歴史があるペルーの代表的新聞だ。リマの中心地、大統領府に近い『エル・コメルシオ』社の前の通
りは、初代社主のミロ・ケサーダの名前がつけられている。
そのミロ・ケサーダ通りにある、コメルシオの記者たちの溜まり場、食堂『ドン・ペドロ』でビールを一緒に飲んできた時、僕はリマにいても面
白くないと、口に出した。
「リマにいても深いところは分からないかもな。どちらにせよ、お前は通信社の記者じゃないんだから、公邸の前に張っていても仕方がないだろう」
ミゲルが勧めたのが、タラポトに行くことだった。
タラポトの村外れを流れるアマゾン河の支流の一つ、ワジャーガ河。その上流は、コカインの原料となるコカノキの栽培地として知られる。人の手の届かぬ
密林は、センデロ・ルミノソやMRTAといった左翼ゲリラたちの潜伏場所にもなっている。
「あの辺りにはMRTAを脱退した幹部が住んでいる。タラポトには友人のジャーナリストがいる。彼を頼って行けばいい」
* * *
ディアナと共に、タラポトの薄暗い空港に到着すると、背が低く筋肉質、眼鏡を掛けたアドルフォ・ファサナンドが出迎えてくれた。オートバイに荷台を溶接したオートバイタクシーに乗り、僕たちはタラポトの街中に入った。
高くて二階か三階建て、ほとんどが崩れ掛けた小さな平屋建ての建物でタラポトの小さな街が形作られていた。空港から街までの道は質の悪いコンクリートで舗装されていたが、街中は土が剥き出しになっている。街の中心のアルマス広場で、オートバイタクシーを降りた。
「早速だな」
アドルフォは唇の端を吊り上げ、僕の後ろをじっと見た。
「三人ついてきている」振り返ると、サングラスを掛けた三人の男が見えた。身長165センチほどで小柄だが、三人とも同じような半袖のシャツを着て腕は太く筋肉が盛り上がっている。
「誰なんだ、アドルフォ」
不審な顔の僕の置いてアドルフォは早足で歩き、広場から角を曲がったところで立ち止まった。
|