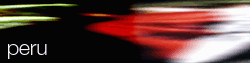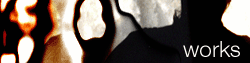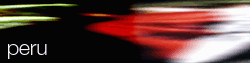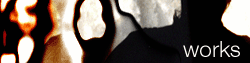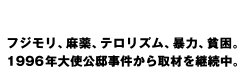|
「なんて綺麗なの」
ディアナが甲高い声をあげた。
窓の外には、碧い水が見えた。ラグナ・アズール、青い湖という名の湖だった。遠くからでもくっきりとした碧色をしている。
ラグナ・アズールの湖畔にあるサウセという村に、元MRTA幹部のシステロ・ガルシアは住んでいるのだ。
車が停められた。前を覗き込むと、無造作に切り落とした枝で作られた遮断機が降りている。道端に、上下、帽子まで枯草色の兵士が銃を持って近付いてきた。
「何だ」
兵士が窓から車内を覗き込んだ。
「ガルシアに取材するために日本から来た」
アドルフォは僕を指さした。
「あのガルシアだ」
アドルフォの言葉に兵士は頷き、遮断機の横にある藁葺き屋根だけの粗末な小屋に向かった。屋根の下では数人の兵士が藁のような毛布を被って横たわっているのが見えた。兵士は一人の男の肩を叩いて起こした。男は眠そうに目を擦りながら立ち上がってこちらに近付いて来た。
「身分証明書を見せろ」
僕はリマの外務省で発行された報道用のパスを見せた。男は文字のところを指でなぞって確認すると、
「このパスと、パスポートを詰め所に置いておけ」
と指示した。戻る時に返却するという。
検問を越えると村だった。タラポトと同じように古い漆喰の壁にさび付いた塗炭の屋根。粗末な民家が低い密度で建てられている。
「ここだ」
アドルフォは一軒の家の前で、車を停めさせた。木でできたテーブルと椅子が並べられていた。食堂のようだった。アドルフォは勝手知ったる顔で、奥に歩いていった。混血の顔をした女性が顔を出した。アドルフォの顔を見ると、再び奥に消えた。
「妻ではないが、ガルシアと一緒に住んでいる女だ」
アドルフォは微妙な笑いを口元に浮かべながら僕の隣りの椅子に腰掛けた。
「すぐにやってくるよ」
しばらくして、奥から恰幅のいい男が現れた。システロ・ガルシアだった。
ペルーによくあるように、原住民インディオと、欧州人の混じり合った混血の顔立ち。目鼻立ちは歌舞伎役者のようにはっきりとしていた。太陽の強い光の元で生活しているためか、顔色はほとんど黒に近い。
「初めまして」
ガルシアは僕に分厚い手を差し出した。
「聞いたか? 昨夜、また事件があったんだ」
ガルシアはアドルフォに向いて言った。
「どんな事件だ」
「いつもと同じ、女がらみだよ」
村のディスコで、つき合っている女性が他の男性と踊っているのを見た男が刀傷沙汰を起こしたという。
「ここはいつも女が不足している」
ガルシアの言葉にアドルフォは頷いた。
サウセの村はずれには軍が駐屯している。兵士たちは訓練の後、村の酒場に繰り出すという。
「酒を飲めば、女が欲しくなる。こんな辺鄙なところまでやってくる娼婦の数は少なく、質も低い。酒を飲んだ兵士たちが村の女を襲うなんてこともある」
ガルシアは椅子に腰掛けると僕の顔をじっと見た。
「何から話そうか」
〜つづく〜
|