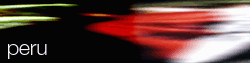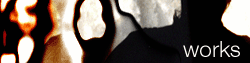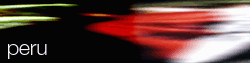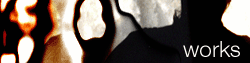|
ブエノスアイレスから高原を追ってアスンションに来た、ライターの寺野、カメラマンの梁川さん、南米に強いカメラマンの三村さんと、アスンション在住のジョニー渡辺さんと韓国料理屋で食事。
現地を熟知する三村さんは一人“紅トンボ”というカラオケへ。僕たちは、ハープのコンサートを聴きに行く。
23時すぎに“紅トンボ”で再び、三村さんと合流した。
三村さんは、すこしきつめのパーマに口髭。風貌はちょっとしたメキシコ人である。テレビのサッカー番組にも時折顔を出す。南米の各地、日本人の報道陣が現れないスタジアムに現れ、写真を撮る。その経験、知識は厖大。そして
威張ることもない。僕たちは一軒目の韓国料理屋から三村さんの話に聞き入って
いた。
僕たちが“紅トンボ”に到着すると、三村さんは、ボトルキープしてあるスコッチを飲んでいた。
三村さんはホルヘ三村という別名を持つ。
僕たちは“紅トンボ”でホルヘとなった三村さんを見ることになった。
「僕はもう酔っていますから、ちょっと歌いますね」
ホルヘはマイクを持つとスペイン語の歌を歌い出した。
そして足はステップを踏む。
足を交差させ、くるりと回る。
タンゴだ。一人タンゴ。
僕たちは思わず「ホルヘ」と叫んでいた。
隣のテーブル、見知らぬパラグアイ人のテーブルからも「ホルヘ、バモス」と歓声と拍手が上がった。
現地の人とのつき合いも面白いが、国外で知り合う“日本人を超えた日本人”とのつき合いも面白い。
|