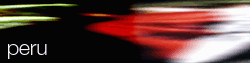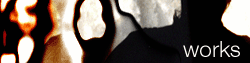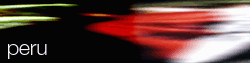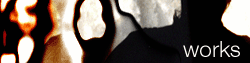|
単行本も一応終わり(実はまだ直しているのだが)、少し時間ができた。
仕事柄どうしても読まなければならない本が多い。うんざりする本も多い。人のことを言えた程文章はうまくはないが、下手な文章を読むと自分にうつるような気がする。
といっても仕事関係はそうも言っていられないので読むことになる。だいたい現役新聞記者の著というのは良くない(もちろん例外はあるが)。中途半端なプライドと権威主義で塗り固められた下手な文章。資料としての価値しかない。読み始めてすぐに放り出したくなる。それをなんとか我慢して読み進めるのが仕事としての読書だ。
自分の趣味としての読書は別だ。読みたい本は部屋じゅうに積み重なっている。
まずは、ずっと前に買って、途中まで止まっていた辻邦生の「西行花伝」を最後まで読み通すことにした。辻邦夫は僕が昔から好きな作家の一人だ。自分が一冊書き終わった後のせいか、文章の作りがさすがに上手いと思う。本の背後にある膨大な取材の時間と蓄積を感じて、圧倒される。一字一句、吟味された言葉づかい、当たり前のことではあるが、自分は足下にも及ばないと思った。下手な文章の本を読むのとは別の意味でゆっくりと読んだ。一文字一文字を深く感じたいと思ったからだ。
そしてもう一冊、先日ノーベル文学賞をとったナイポールの「インド・闇の領域」。
ナイポールはインド移民の子孫、トリニダード・トバコ出身で英国在住の作家だ。
もう十年以上前、大学の春休みを利用して、タイ、バングラデシュを経由してインドに行った。初めての国外旅行だった。カルカッタから列車で、ヴァラナシー。一ヶ月近い滞在のほとんどをヴァラナシーで、シタールという楽器を習って過ごした。
インドは確かに興味深い国だった。しかし、中に入れない何かがあった。だからその後もう一度行きたいとも思わなかった。中に入れない何かは何だったのか、異邦人を戸惑わせる社会の緩慢な動きについて、ナイポールの本で少し分かった。
|