


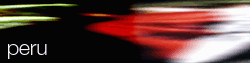
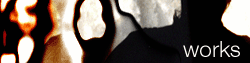
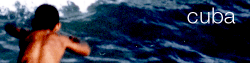

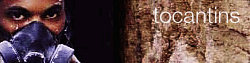
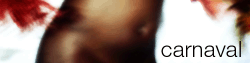
 |
 |
 |
|
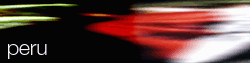 |
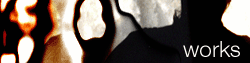 |
||
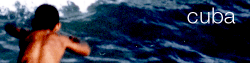 |
 |
||
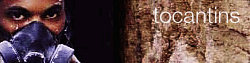 |
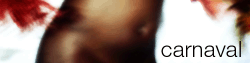 |
||
 |
田崎健太/Kenta
Tazaki......tazaki@liberdade.com
1968年3月13日京都市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、小学館に入社。『週刊ポスト』編集部など を経て、1999年末に退社。サッカー、ハンドボール、野球などスポーツを中心にノンフィクションを 手がける。 著書に『cuba ユーウツな楽園』 (アミューズブックス)、『此処ではない何処かへ 広山望の挑戦』 (幻冬舎)、『ジーコジャパン11のブラジル流方程式』 (講談社プラスα文庫)、『W杯ビジネス3 0年戦争』 (新潮社)、『楽天が巨人に勝つ日−スポーツビジネス下克上−』 (学研新書)。最新刊は 、『W杯に群がる男たち―巨大サッカービジネスの闇―』(新潮文庫)。4月末に『辺境遊記』(絵・下 田昌克 英治出版)を上梓。 早稲田大学非常勤講師として『スポーツジャーナリズム論』を担当。早稲田大学スポーツ産業研究所 客員研究員。日本体育協会発行『SPORTS JUST』編集委員。愛車は、カワサキZ1。 |
|
| 2006..........2005..>> 12.>11.> 10.>.9.> 8.> 7.> 6.> 5.> 4.> 3.> 2.> 1..........2004 |
|
|
|
|
|
|
|
(c)copyright
KENTA TAZAKI All rights reserved.
|