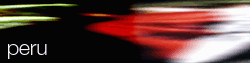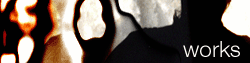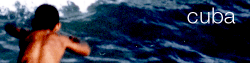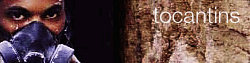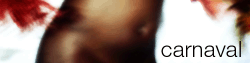|
1968年3月13日京都市生まれ。ノンフィクション作家。早稲田大学法学部卒業後、小学館に入社。『週刊ポスト』編集部などを経て、1999年末に退社。 |
2012年5月29日
あっという間に五月が終わってしまう。
原稿執筆や取材、打合せの他、長良じゅん会長の本葬など様々なことがあった。ようやく先週末で一段落がついたので、伊豆まで愛車カワサキZ1で走りに行って来た。
本当は日曜日から一泊で仙台に行くつもりだったのだが、朝起きると前日のフットサルのせいなのか上半身がこわばり、息苦しい。とても、仙台までオートバイで行く気になれなかった。
身体は疲労だったようで、夜になると回復した。梅雨に入る前に、オートバイに乗りたいと思うと眠れなくなり、朝に原稿を届けるとそのまま首都高に乗って西に向かった。
ぼくが大学生の時、伊豆は走り屋で溢れていた。知り合いに誘われて、ぼくも峠を攻めに行っていたものだ。平日ということもあるだろう、伊豆スカイラインは車通りがない。革つなぎを来た大型オートバイの集団とすれ違っただけだった。そして夏の陽気――。
ところが――。
日が陰ってきたと思うと、空には黒が混じった雲が増えていた。気温が下がり、肌寒い。そして、強い雨が降り出してきた。
大粒の雨で視界が遮られ、前方の道路からは白い湯気が立ち上っている。
とはいえ、伊豆スカイラインは山の中を走っているので、雨宿りをする場所はない。ひたすら、先を急いだ。ようやくオートバイを停めることが出来たのは、十国峠のサービスエリアだった。軒の下に駆け込んで自分の姿を見ると、ジャケットはまだらに濡れていた。さらに、地面からの跳ね上がった水を受けたジーンズは膝から下がべっとりと濡れていた。雨の中を走るとみじめな思いになる。
しばらくすると雨はあがり、雲の切れ間から太陽が見えた。
オートバイにまたがると、タンクの上の水滴がきらきら輝いている。エンジンを掛けて走り出すと、雨が通り過ぎた後の道路は独特の匂いがした。先ほどまでのみじめな気持ちは一瞬にして消え去った。
ああ、これだと思った。
雨が降れば、密閉された車の方が快適かもしれない。しかし、オートバイに乗っていると色んなことを感じられる。気持ちのいい太陽、雨の匂い、湿気――感覚が研ぎ澄まされるから、ぼくはこの不便な乗り物から離れられない。
人生と同じだ。車の中で雨風から守られた人生もいいだろう。でも、ぼくはそれでは面白くないのだ。

ぼくの後輩が大麻で逮捕された。ぼくとは編集部在籍は重なっていないが、付き合いのある数少ない編集者でもあった。
たかが大麻、と言う気はない。大麻吸引を認めている国はあるが、法治国家である以上、国民は法律を守るべきだ。後輩を擁護する気はない
ただ――。
昔の週刊誌編集部のトイレにはマリファナの吸い殻が落ちていたなどという話もあった。枠から外れた男たちが集まっていたのだから、さもありなん。そうした荒くれた、猥雑な雰囲気が週刊誌からなくなって久しい。今やすっかり老人向けになって、棘を失った週刊誌を見ると、ちょっと寂しいという気持ちもある。
2012年5月4日
別れはいつも突然に来るものだ。
携帯電話に気が付いたのは十六時頃だった。
普段から原稿に集中している時は、携帯電話の音を切って、放っておく。ちょうど一段落した頃、携帯電話にメールが届いているのに気が付いた。知り合いの記者からだった。「もしかしたらご存じかもしれませんが」と長良じゅん会長の死を知らせる内容だった。すぐに電話を入れると、事故とのことだった。信じられない思いで、何人かの知り合いに確認した。残念ながらその情報は正しいようだった。
長良会長には世話になりっぱなしだった。
小学館の社員時代、勝新太郎さんの関係で、長良さんと知り合った。後から芸能界で非常に力を持っている人だと編集部の人間から教えられた。あまり物怖じしないのが良かったのかもしれない。初対面の時から、昔の興行師の話など、きさくに話をしてくださった。
当時長良さんがマネージメントをしていた小林旭さん、長良さん、内舘牧子さん、そして編集部の上司と共に酒をご一緒させてもらったこともあった。輸入自動車の名前のついたビルの上にある高級クラブから六本木のクラブに移動して、朝まで飲むことになった。途中から石橋貴明さんも加わり、芸能界というものを肌で教えて貰った。
その後、ぼくが勝さんの本を書きたいと手紙を出すと、「会いに来いよ」と電話をもらった。
「俺はな、勝さんのことを書いてくれるのが嬉しいんだよ」と話は尽きなかった。
「美空ひばりと勝新太郎に関しては、嫌な思い出が一つもないんだ。大好きな人だった」
美空ひばり、水原弘、そして勝新太郎、登場人物がみな面白いのだ――。
非常に律儀な人だった。礼状を出すと必ず返事が来た。本の参考になるかもしれないからと、自分が出演したラジオ番組の収録が送られてきたこともあった。勝さんのことを書かれるのは気が進まないという玉緒さんの間にはいってくれたのも長良さんだった。
本の完成は震災もあり、予定よりもずいぶん遅れた。
どこかで長良さんに連絡をいれないといけないと思っていた。そんな時、帝国ホテルであったパーティに出席すると、たまたまエレベータで長良さんと出くわした。下の階で美空ひばりさんの二三回忌をやっていたのだ。「不思議な縁もあるものだね。勝さんが引き合わせてくれたんだよ」と、エレベータに乗りながら、立ち話をすることが出来た。
だから『偶然完全 勝新太郎』が出来上がった時、真っ先に連絡を入れた。
出版パーティを開くので、是非出席して欲しいと思っていた。なかなかこうした会には出席しないと聞いていたので、秘書を通して出席の返事をもらった時は嬉しかった。
11月29日、勝さんの誕生日、長良さんは勝さんの息子の雄大さん、娘の真粧美さんたちとお見えになってくれた。
「挨拶だけは勘弁してくれよ」
と壇上にはあがってもらえなかったが、終始にこやかだった。
あのパーティが長良さんとの最後の別れになってしまった。
いずれ昭和の興行について詳しく話を聞かせて貰うつもりだった。
「俺なんか話すことはないよ」と長良さんは謙遜しながらも「それよりも、また飲もうよ」とおっしゃってくれていた。それももう叶わなくなった。
『偶然完全』のプロローグにも長良さんの話が出てくる。毎日の行き帰りで東京タワーを見ると、勝さんを思い出すというくだりだ。ぼくもこれからは、六本木のロアビル近くを通る時、長良さんを思い出すことだろう。天国で勝さんと旨い酒を飲んでいるだろうと。
2012年5月1日
あっという間に四月が終わってしまった。
Facebookやtwitterは書いていたものの、ホームページは半月ほど放置状態だった。理由は簡単、写真が撮れていないのだ。文字だけで更新するのもあれだな、と思っているうちに、時間が経っていた。
先月17日、18日と大阪市特別顧問の中田宏さんに同行して、大阪へ出張していた。六本木のテレビ朝日での収録からそのまま羽田空港に直行、搭乗時間ぎりぎりにVIP入口から入った。そうした配慮を受けないと間に合わない程、タイトなスケジュールだった。彼と行動を共にしていると、政治家という職業の大変さを思い知る。彼はこう言う。
「橋下さんもぼくも考えは同じなんですよ。政治家なんてやるもんじゃない。やることをやったら、さっさと辞めたい。しがみつきたいと思う人間の気がしれない」
彼の気持ちはなんとなく理解できる。真面目にやれば嫌われることばかりだ。とても子どもにやらせたいと思う職業ではない。世の中に二世、三世議員が溢れている理由がわからない。
夏前に刊行予定だった短編集は、版元の希望で形を変えることになりそうだ。長い本は売れないと言われれば……。正式に形が決まればここで報告したいと思っている。近々、仕上げのためにどこかで温泉に籠もるかもしれない。
5月10日発売の『サッカー批評』(双葉社)でジーコのインタビューを書いている。書き出しはこんな感じだ。
〈人はなかなか本音を話さないものだ――。特に多くの人間から取材を受けてきた、〝取材慣れ〟した人間に話を聞く時は注意が必要である。過去にどこかで話した内容をただ繰り返すことも少なくない。彼らには、きちんと向き合い、繰り返し会い、しつこく話を聞かなければならない。
ぼくが初めてジーコにきちんと話を聞いたのは今から一七年前、一九九五年一月。母国ブラジルのリオ・デ・ジャネイロに作ったサッカーセンターの開幕式数日前のことだった〉
彼は現役時代から世界中から注目されるスーパースターだった。自分がどれだけの影響力があるのか自覚しているので、話す相手を良く見ているし、言葉を選んでいる。だから、インタビューで本音を聞き出すのは難しい対象と言える。ぼくがポルトガル語を理解し、ブラジルで生活した経験があること、彼を追いかけてイスタンブール、モスクワまで出かけたこともあるだろう。これまで「二〇〇六年W杯の日本代表には腐ったミカンがいた」等、ジーコは様々な話をしてくれた。
原稿にも書いたように、ぼくはジーコに二〇〇六年以降も含めて、日本人ジャーナリスト(もしかしてブラジル人も含めてかもしれない)として一番、きちんと話を聞いてきたという自負がある。今回の取材でも彼は日本代表と対戦するイラク代表監督でありながら、可能な限り話をしてくれている。

大阪にて。場所がベタ過ぎるやないか~中村君っ。取材は『GQ』に掲載予定。撮影は中村治君。この写真はぼくのCanonS95使用。