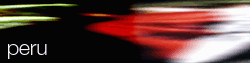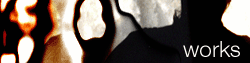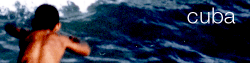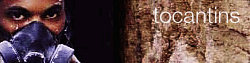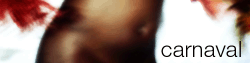|
1968年3月13日京都市生まれ。ノンフィクション作家。早稲田大学法学部卒業後、小学館に入社。『週刊ポスト』編集部などを経て、1999年末に退社。 |
2013年5月17日
ぼくの考えるノンフィクションは、細部の描写の積み重ねである。
時に非常に些細なことまで調べ、執筆の材料を集める。良心的に人間や事象を描こうとすればするほど、使われることのない取材は積み重なっていくものだ。その無駄は取材側に理解されにくい。しつこく細部を尋ねられることを、嫌がる被取材者も多い。時間に追われる人間、細かなことを語ると、ぼろが出る人間はその傾向が強い。〝政治的な〟人間などその典型だ。そのため、政治には興味はあったが、自分の手法で描くのは難しいとも思っていた。
ところが中田さんは少々違っており、細かな質問にもきちんと答えてくれた。
ぼくの取材方法では細かなところが重要なのですと説明すると、「忘れっぽいのでこうやってつけているんだよね」と日記を開いて教えてくれることさえあった。
週刊誌の誤った醜聞で彼とその家族は傷つけられていた。初めは彼についてきちんとした原稿を書き、誤解を解く一助になれればという気持ちだった。それがかつて週刊誌で働いていた人間としての責務であるとも思っていた。
そのうち、彼は橋下徹氏と近くなった。ただ、最初は全面的な信頼ではなかった。橋下氏の政治家としての覚悟は高く評価するものの、皮膚感覚として相容れない面があるようにも見えた。それが大阪市特別顧問に就任してから急速に変わった。中田さんを通して橋下という政治家を描けないかと思ったのは、その頃だ。
橋下氏が大阪でやろうとしていることの多くを、中田さんは横浜市ですでに実践していた。何かとワイドショー的に香りのある橋下氏に中田さんを重ねると、その本質が浮き上がってくるように思えたのだ。
二〇一一年十二月末、写真家の横木安良夫さんの紹介で『GQJapan』の鈴木正文編集長に会う機会があった。鈴木さんから「何か書きたいものはありますか?」と尋ねられ、ぼくは迷わず「中田宏さんを通して橋下徹を書いてみたい」と答えた。
そしてGQでは三回原稿を書くことになった。この原稿に取材を加え、再構成したのがこの『維新漂流 中田宏は何を見たのか』である。

そして、今日見本が届いた。デザインは『偶然完全 勝新太郎伝』に引き続いてniwanoniwaの三村漢君。帯の中田さんの写真は中村治君によるものである。 『維新漂流 中田宏は何を見たのか』(集英社インターナショナル)は1575円(税込)、5月24日発売です。

2013年5月8日
ぼくが中田宏さんに初めて会ったのは、二〇〇二年のことだった。当時、衆議院議員だった彼が横浜市長選挙に出る直前のことである。この時は、本当にすれ違った程度だった。中田さんは不利だと見られていた市長選に勝ち、政令指定都市で史上最年少の市長となった。そして横浜市の財政を立て直し、改革派若手市長として広く知られるようになった。
その後、ぼくが再会したのは、二〇一〇年八月末のことだ。彼は公約通り二期で横浜市長を辞して、日本創新党という新党を山田宏さんと一緒に立ち上げ、参議院選挙に出馬、落選していた。落選の原因は色々とある。その一つは、週刊誌による醜聞記事だった。後に裁判で明らかになるように、これは全く根も葉もない記事だった。この二度に渡る連載記事により、清潔な青年市長という彼の印象はすでに霧散していた。横浜市長を辞任した経緯をきちんと説明しなかった(これには理由がある!)こともあり、胡散臭い政治家と世間から思われている節もあった。
正直に言うと、ぼくも彼に関する醜聞を半ば信じていた。全てが真実ではないとしても、幾らかの真実が混じっているだろうと思っていたのだ。この年の夏は三十度を超える猛暑が続いていた。中田さんと再会した日も窓硝子越しに照りつける強い太陽が照りつけていたことを覚えている。そんなむっとする午後、四時間程度話をした。
ぼくは彼に対する〝疑惑〟を不躾なほど突っ込んで聞いた。被取材者の中には病的な嘘つきが混じっていることがある。だから、ぼくはかなり疑って話を聞く習癖がある。そんな自分でも彼の話は筋が通っており、ほぼ正しいと感じた。
それ以来、ぼくは毎月、彼に話を聞くことなった。そして、〝ほぼ〟という副詞はすぐに消えた――。
この時はまだ彼について長い原稿を書く気はなかった。週刊誌に携わった経験のある人間として、彼に対する記事に責任を感じていた。少しでも彼の名誉回復の手助けとなる、真実を伝える原稿が書ければという気持ちだった――この続きはまた来週にでも。

ぼくは自分の興味のあることだけを取材して原稿を書いてきた。ただ、本当に好きな幾つかのことは、仕事にしていない、いや出来ていない。例えば、オートバイである。だから同好の士と出会うと、話が止まらなくなる。その中の一人がエイ出版の角社長だ。
今回は角社長の紹介で、Z1のムックに登場することになった。角社長を繋いでくれたのは、タケ小山さん(平田研究室で、ケンドーカシンと同期!)である。
〝あの〟ライダースクラブのムックに出られるなんて、という気分だ。タケさんとの対談場所は最近お世話になっている伊藤君の好意で、世田谷通りのSCMを借りることが出来た。取材の日は、早起きしてオートバイを磨いた。今はかなり綺麗になっているはずである。やっぱりオートバイの話をするのは楽しい。話が尽きないのだ。
どこかでカワサキZ、あるいはオートバイについてコラムでも書かせてくれればいいのだが…。
エイ出版発売の『kawasaki Z book』はぼくの単行本とほぼ同じ、今月末発売日です。
2013年5月2日
一昨日、四月三十日の夕方に分厚い単行本のゲラを出版社に届けた。いわゆる責了である――。
単行本に限らず、雑誌でもゲラは何回も読み返し、修整を入れる。細々としたところが気になってしまうので、期日を区切って戻すことにしなければ、ずっと抱えていることになるだろう。もうこれでいい――そう思い切ることが大切である。
本や雑誌となってからしばらくは自分の原稿を読み返すことはない。なぜならば、こう直せば良かったと後悔するのが嫌だからだ。
今回の本は中田宏さんを中心に、維新の会を描いている。意外かもしれないが、二〇〇〇年に出版社を退職した時、書いてみたいテーマを書き出してみたことがある。その中の一つに政治、そして選挙があった。
ただし――。
ぼくは政治家ほど取材しにくい人種はいないと思っている。
仕事柄、様々な人の話を聞く機会がある。人は必ず嘘をつくものだと思っている。積極的に騙そうとしなくとも、人にはこう見られたい自分像というのがある。都合の悪いことは伏せて、自分の言いたいことを話す。
中でも、政治家は最悪だ。正確には政治家的な人間と言い換えていい。世界中どこでも、権力志向の強い人間は〝政治家的〟だ(FIFA会長のジョアン・アベランジェなどは典型的だ。『W杯に群がる男たち』の取材でぼくはどれほど苦労しただろう!)。
彼らはこちらの投げかけた質問をはぐらかし、自分の言いたいことだけを話し続ける。特に街頭演説などで一方的に話することに慣れている政治家は、立て板に水のごとく使い古された言葉で空間を埋め尽くしてしまう。
ただ、中田宏さんは少々違っていた――。
ぼくが彼を書くようになったきっかけについては、またの機会に。

本の最後は先月末の維新の党の党大会に触れている。現在進行形の話を書くのは本当に難しい。