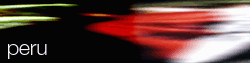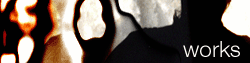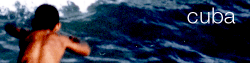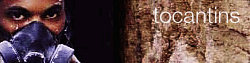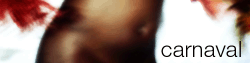|
1968年3月13日京都市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、小学館に入社。『週刊ポスト』編集部など を経て、1999年末に退社。サッカー、ハンドボール、野球などスポーツを中心にノンフィクションを 手がける。 著書に『cuba ユーウツな楽園』 (アミューズブックス)、『此処ではない何処かへ 広山望の挑戦』 (幻冬舎)、『ジーコジャパン11のブラジル流方程式』 (講談社プラスα文庫)、『W杯ビジネス3 0年戦争』 (新潮社)、『楽天が巨人に勝つ日−スポーツビジネス下克上−』 (学研新書)。最新刊は 、『W杯に群がる男たち―巨大サッカービジネスの闇―』(新潮文庫)。4月末に『辺境遊記』(絵・下 田昌克 英治出版)を上梓。 早稲田大学非常勤講師として『スポーツジャーナリズム論』を担当。早稲田大学スポーツ産業研究所 客員研究員。日本体育協会発行『SPORTS JUST』編集委員。愛車は、カワサキZ1。 |
2008年7月30日
今日開幕したハンドボール実業団選手権の取材のため、昨日から沖縄に来ている。
今季から、田場裕也が立ち上げた「琉球コラソン」が実業団リーグに参加する。
沖縄でのクラブチーム設立について、田場から相談を受けていたが、僕は賛成ではなかった。
現在のハンドボール界は、クラブチームの経営が成り立つ枠組みが出来ていない。
サポートしている企業の側は、ハンドボールは、あくまで社員の福利厚生の一環であり、利益を出すことが必要ではない。
実業団リーグは、健全経営のために利潤確保が必要な、クラブチームの参戦を念頭に置いていない。
そもそも、この実業団リーグは、選手の身分についても曖昧だ。社員選手と外国人選手、あるいは契約社員、業務を全くしない“プロ契約”選手が混在している。それぞれの立場で、抱えている問題が異なっている。
田場がクラブを立ち上げた時は、そこまで深く考えていなかっただろう。そして、困難に面しながらも、よろよろと走り出した。
「琉球コラソン」を描くことは、ハンドボール界、そしていわゆるマイナースポーツの問題点をあぶり出すことだ。誰かが、田場たちの苦闘をきちんと残さなければならない。
今回の取材は、複数のメディアに掲載予定。詳細は、また。

初戦となった対ホンダ熊本戦、ほとんどの時間で先行されていたが、終了間際に追いつき、村山が決勝シュートを決めた。村山、岡田たち、チーム立ち上げから所属していた選手と、新たな加入した水野たちが少しかみ合ってきた。苦労を知っているだけに、勝利の瞬間は、僕も少し涙が出そうになった。
2008年7月24日
帰国してから慌ただしい日々が続いている。日曜日は、荒木町「オブラディ」でフォークのライブがあったので、一曲飛び入りすることになった。当日の夕方から、泉谷しげるさんの「黒いカバン」のコードを採って、前日オープンした「荒木町ハッピースタジオ」で軽く練習し、歌ってきた。
「荒木町ハッピースタジオ」についてはまたの機会に。
その後は、来週からの出張に備えた打合せや原稿書き−−のはずだったが、かなり出歩いている。まずい状況に追い込まれている。
先週のサハリン(樺太)取材は、8月4日(月)発売の週刊ポストに掲載されることになった。是非、一冊購入お願いします。

漁船の墓場。

コルサコフにて。
2008年7月18日
前略
本日、無事にサハリンより戻りました。
ソビエト時代の話を聞いていたので、入国審査官や警官などに警戒していたのですが、ペレストロイカ以降大きく変わったのか、非常に親切にしてもらいました。
ただ−−。
レーニン広場の芝生で泥酔している男がいました。二人組の警官は寝ている男に近寄ると、男の脛を強く踏みつけました。男はばねのように起き上がり、警官を見る顔がゆがんでいました。警官は無表情のまま、男を無理矢理立たせ、尋問を始めました。
政府が大きな権力を持っている国を垣間見た思いでした。
今回の取材は、来月発売の「週刊ポスト」に掲載予定。戦後、島に取り残された
朝鮮系住民を中心に、この島が辿ってきた悲しい歴史、そして未来を描くつもり
です。掲載号が決まれば「liberdade.com」に書きます。
取り急ぎ。

王子製紙工場跡
2008年7月15日
昨日の夕方、コルサコフを経由して、ユージノサハリンスクに到着した。
稚内からコルサコフへ向かうフェリーの中で、モスクワから来た写真家と仲良くなった。彼らは、サハリンで写真をとった後、稚内に足を伸ばし、足袋や工事現場用の蛍光灯など不思議なお土産を買っていた。
彼らはなかなか才能ある写真家だった。サハリンの北部の漁村などの写真を見ると、モスクワに住む彼らにとっても、サハリンは創造意欲を掻き立てる、不思議な場所であるようだった。
帝政ロシア時代、この島は流刑地であった。ロシア人の他、アイヌ人、日本人などが混在して住んでいたと思われる。その後、日本の領土となり、多くの日本人、徴用された朝鮮人が島を開拓した。第二次世界大戦の後、島はソビエトが領有することになり、日本人は引き上げ、朝鮮人が残された。
そして、ロシア人が増えたが、しばらくの間は、貧しい島であった。
近年、天然ガスプロジェクトが始まり、島は急激に変わりつつある。日本から四十キロしか離れていない、最も近いヨーロッパの辺境に生きる人々の姿を描きたいと思っている。

かつて白浦と呼ばれたブズモーリエに残された日本統治時代の鳥居。
奥に小さく写っているのは、「シモダノビッチ・ヤバコフ」こと下田画伯。

ブズモーリエの駅にて。
今回は、デジタルのGRDと銀塩のGR1vのリコー二台体制。
銀塩のGR1vで撮った写真は戻ってからのお楽しみである。
2008年7月13日
暑い東京を出て、空路で稚内へ。
稚内は、日本最北端の駅がある街だ。小雨が降っており、肌寒いぐらいだった。東京とは全く違った天気である。
日曜日のせいもあるのだろうが、商店街のシャッターはみな降りていた。店の看板には、キリル文字が書かれている。七、八年前まではロシアの蟹漁船が到着し、街の人口4万人と同じぐらいの人が行き来していたのだという。
明朝のフェリーで、サハリンへ向かう。今回も、栗駒地区に引き続き、絵描きの下田昌克と写真の太田真三氏と一緒に、「週刊ポスト」の不定期連載の取材である。
ロシアは最初に意識した「外国」だった。僕は京都市内で生まれているが、小学生の低学年の三年間は、京都府の日本海側の街、舞鶴で過ごしている。
横浜など太平洋側の港町であれば、最初に出会う西洋人はアメリカ人であったろう。当時、舞鶴はソビエトとの交易が盛んだった。サハリンからも定期便が来ていたはずだ。街には大きな身体をしたロシア人が歩いていた。ソビエトは、社会主義国家で得体が知れない印象があった。テレビドラマで見る“ガイジン”とは違って陰気な感じがした。
僕の通っていた小学校では、小学六年生になると、学年で最も優秀な生徒が一人、夏休みの間、ソビエトへ留学できることになっていた。僕は港で船を眺めるのが好きだった。どこか知らない国に行きたくて仕方がなかったのだ。
成績は常に良かったので、六年生になった時、留学に行く最有力の候補の一人であると自分では、思っていた。毎年、夏休みが始まる前の全校集会の時、ソビエトに行く生徒の名前が呼び上げられ、壇上で挨拶した。僕は自分が名前を呼ばれる絵を思い浮かべていた。
ところが、僕はその前に、転校することになった。
あれから30年ほど経って、あの時の夢が叶う。

恐らくかつては栄えていたであろう、稚内駅の近く。
まさにここは「さいはて」なのだ。
2008年7月6日
昨日から、地震被害に遭った宮城県の栗駒に来ている。新幹線の駅がある「くりこま高原」や近隣の街を歩いていても地震の痕跡はない。
あれだけ大きな地震だったのにと不思議な気持ちになる。
避難所で生活している、被害の大きかった耕英地区の方々に話を聞いている。開拓民として大地を切り開いた人たちには、ブラジル移民の一世の人たちに通じる逞しさがある。辛い時に明るく振る舞える、強さを感じた。
今回は、絵描きの下田昌克と一緒にやっている、「週刊ポスト」の不定期連載。来週月曜日発売号に掲載される。

避難所の笹に吊された短冊。
この「とくめいきぼう」君は、別の短冊に「早く道路が通れるようになりますように」と書いていた。
2008年7月4日
今日は早稲田のスポーツジャーナリズム講座の今季最後の授業。この授業では毎月課題を出している。それを僕が、講評してきた。
今回は、読み応えのあるものが多く、当日の朝まで授業でどれを取り上げればいいのかと頭を悩ませた。
4月の授業で話したことだが、文章を書くことは、車の運転に似ていると僕は思っている。つまり、ほとんどの人間は教えを受ければきちんと車を運転することができるように、誰でもしっかりとした文章を書けるということだ。
文章もきちんと学べば、ほとんどの人はライターや記者として書けるレベルに到達することができる。作家性があるか、ないかは別の問題である。
プロのドライバーでも、タクシー運転手からF1レーサーまで運転のレベルがあるように、文章にもレベルがある。
かつては名刺を作れば誰でもライターになることができると言われた。インターネットの時代では、名乗ればその時点で、ライターになれる。
ただ、きちんと学ばずに書くことは、、運転技術を学ばずに公道に出てしまうようなもので危なっかしい。何より、技術がなければ、長続きしない。
ごく一部の天才的な作家には訓練の場は必要ないのかもしれないが、昔の純文学の作家は、同人誌で書くことで鍛えられた。今では、良心的な編集者とのやり取りがそれに当てはまるのかもしれない。
雑誌ジャーナリズムの世界では伝統的に、明確な教育機関はなかった。一定の水準以上の編集部で、働きながら経験則で鍛えられていく。僕の場合、社内の上司や先輩はもちろんだが、担当した作家やジャーナリストに多くのことを学ばせてもらった。
早稲田のスポーツジャーナリズム講座がどこまでそうした場に近づけたかはわからないが、僕の他にも色んな人が来て話をした。それを学生たちが吸収したことが、レポートに現れていた。
この講座の最後の授業では広山望選手の話をしようと決めていた。
僕は彼について 「此処ではない何処かへ 広山望の挑戦」 という本を書いている。僕が彼と出会ったのは、2001年のことだった。パラグアイ、ブラジル、ポルトガル、フランス −− 彼の人生を併走することで、僕は多くのことを学んだ。
一番印象に残っているのは、2002年W杯の前のことだ。広山選手は所属チームが決まらなかったこと、そして労働ビザが下りなかったことから、ブラジルのレシフェで一人で練習に参加していた。国外出張に出かける時は、出版社と話をして、経費を集めて出かけていた。この時の日本のメディアは、W杯一色で、代表から落ち、クラブの試合に出ることもできない広山選手の記事を載せようというメディアはなかった。
ただ、僕はそれでも行かなければならないと思った。異国の地で踏ん張っている彼の助けに少しでもなりたいと考えたのだ。彼がドイツで世界選抜の試合に出るというので、自費でドイツに向かい、そのまま一緒にブラジルへ行くことにした。
ドイツでは、彼の練習に付き合い、ゴルフ場を走った。どうも入ってはいけない場所だったようで番犬に追われたこともあった。ブラジルでも毎日一緒に行動した。長い時間を過ごしたが、ほとんど取材らしい取材をしなかった。その表情を見るだけで、僕は多くのことを感じることができた。
単行本の原稿を書き上げた後も、出版すると約束した出版社が降り、別の出版社を探さなくてはならなかった。そうした過程で、僕は書き手として成長した。だから、最後は彼のことを話すべきだと思ったのだ。

「此処ではない何処かへ」の表紙写真として使った写真。モンペリエの丘の上で撮影した。

2002年、ドイツで世界選抜の一員としてピッチに入る、広山選手。
学生のレポートの出来がいいので、優秀作品に賞品を出したいと思った。広山選手に電話を入れて、彼が着用したヴェルディのユニフォームを提供してもらうことにした。レプリカと本物は重みが違う。もらった学生にとっては、宝物になるだろう。。